「サッカーの練習は一生懸命しているのに、なぜか試合で活躍できない」
そんな伸び悩みに直面している小学生は少なくありません。また、そばで見守る保護者の方も「何か手助けできることはないか」と悩んでいるのではないでしょうか。
技術の習得は、量だけでなく「質」が重要です。とくにドリブルやシュートといった個人スキルは、正しいフォーム・判断・身体の使い方を理解していなければ、なかなか上手くなりません。
本記事では、これまで300名以上の小学生指導に携わってきた現役コーチ監修のもと、サッカーが上手くなるための方法や自主練方法を紹介します。
今すぐ実践できる自主練の解説動画も紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

TORIDENTEストライカースクール代表
比嘉 大夢(ひろコーチ)
関東と沖縄を拠点とする「TORIDENTEストライカースクール」の代表。SNS総フォロワー18万人。小学生からサッカーを始め、中学時代にはJ下部組織に所属。高校時代には選手権出場経験があるほか、プリンスリーグチーム内得点王・アシスト王を記録。これまでパーソナルレッスンで300名以上の小学生を指導実績あり。

SOCCER KIDS編集部について
SOCCER KIDSは、サッカーをする少年・少女に夢を与えられるよう情報を発信するメディアです。現役コーチ監修のもと、お子さんと保護者双方のお役に立てるよう丁寧に編集を行っています。
>>SOCCER KIDS編集部について
なぜサッカーが上手くならない?小学生がつまずく5つの理由

一定のスキルを身につけた子どもでも、ある時期から急に伸び悩むケースは珍しくありません。その背景には、技術や身体的な問題以上に「日々の取り組み方」や「練習環境」に原因が潜んでいることが多くあります。
ここでは、これまで300人以上の選手を育成して見えた小学生がつまずく5つの理由を解説します。
- ボールを触る時間が圧倒的に足りない
- 練習が「考えずに繰り返す」だけになっている
- 自主練の習慣がない
- 苦手を避けて得意な練習だけやっている
- 成長を「感じる仕組み」がない
 ひろコーチ
ひろコーチ小学生の成長は早くも遅くも、日々の積み重ね方次第で大きく変わります。それぞれの課題について、どのように見直すべきか順に見ていきましょう。
1.ボールを触る時間が圧倒的に足りない
サッカーが上達するうえで、最も基本的で欠かせないのが「ボールタッチの総量」です。
どれだけ優れた練習メニューを取り入れても、そもそもボールに触れる回数が不足していれば、技術はなかなか定着しません。とくに少年団では、週1〜2回の活動にとどまることも多く、日常的にボールに触れる時間が極端に少なくなりがちです。
さらに、チーム練習が全体指導中心の場合、個々がボールを扱う時間は限られ、待ち時間や指示を聞いている時間が多くを占めることもあります。
その点、伸びる子どもたちは以下を活用してボールに触れる時間を確保している傾向があります。
- 個人レッスン
- サッカースクール
これらは単に練習時間を増やすだけでなく、個別にボールタッチの質を高められる場としておすすめです。
とくに個人レッスンでは、一人ひとりの課題に合わせて密度の高い練習が可能です。サッカースクールは、試合に直結するスキルの向上を目的としており、個人スキルを磨くためのトレーニングが受けられます。
サッカーの個人レッスンの効果が知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。
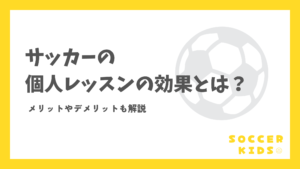
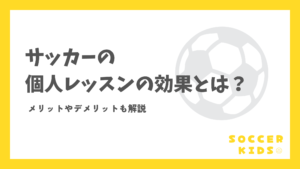
2.練習が「考えずに繰り返す」だけになっている
チーム練習を見ていて「ただ同じ動きを繰り返しているだけ」と感じたことはないでしょうか。
多くの小学生に共通するつまずきのひとつが、動きの意味や目的を理解しないまま練習を続けてしまうことです。
例えば、ドリブル練習でも「なぜそのフェイントを使うのか」「どんな場面で効果的なのか」といった部分がわかっていなければ、試合ではまったく使えません。ただ繰り返すだけの練習では、技術も判断力も育ちにくくなります。
- 練習後に「どんな場面でその動きを使いたいか」を言葉にしてみる
- 成功やミスの理由を一緒に整理して次に活かす視点を育てる
- 正解を教えるのではなく、自分で考える感覚を大切にする
ただの反復練習を思考をともなった学びの時間に変えることで、試合での判断力やプレーの精度も伸びていきます。
3.自主練の習慣がない
小学生年代のサッカー上達には、自主練が大切です。
週に1〜2回のチーム練習だけでは技術や判断力を身につけるには不十分であり、なかなか上達しません。
実際に、プロ選手も幼い頃から自主練を習慣にしています。イングランド代表のフィル・フォーデン選手は「毎日ボールを持って外に出ていた」と話しており、日本代表の久保建英選手も、学校から帰宅後は毎日のように自主練に取り組んでいたことで知られています。
共通しているのは、指示されて動くのではなく、自分で考え工夫しながら取り組んでいた点です。
- 毎日決まった時間に短く取り組み、習慣として定着させる
- 頑張りを言葉にして認め、小さな成功体験を積み重ねる
- メニューを絞って「できる」「楽しい」と感じられる内容にする
上達のスピードは、日々どれだけボールに触れているかで決まります。お子さんのペースに合わせた自主練の環境づくりが、将来の成長につながっていくでしょう。
4.苦手を避けて得意な練習だけやっている
小学生のうちは、好きなプレーや得意な動きに偏って練習しがちです。
例えば、利き足のドリブルばかりを繰り返したり、上手くできるフェイントだけを選んで取り組んだりする場面がよく見られます。しかし、試合では苦手な場面にも必ず直面します。
相手の守備が強いときや、逆足でのプレーが求められるときに対応できなければ、プレーの幅は広がりません。
- 1日の練習に「苦手なことに1回だけ挑戦する時間」を取り入れる
- できたことだけでなく「チャレンジしたこと」を言葉で認める
- 上手な選手の動画などを一緒に見て、具体的な動きをイメージさせる
実際、技術が伸びていく子どもほど「できないこと」にも積極的にチャレンジしています。苦手を避けるのではなく、失敗を受け入れて繰り返すことで、プレーの安定感が増していきます。
5.成長を「感じる仕組み」がない
子どもが継続して努力するうえで「できるようになった」という実感は大きな原動力になります。
自分の成長を感じられない状態が続くと、やる気が下がり、練習に前向きに取り組めなくなってしまいます。
とくに小学生年代は、練習メニューをこなしても「上達しているのかどうか」が本人にはわかりづらいこともあるでしょう。ただ頑張っているだけの状態では達成感を得にくく、モチベーションも続きません。
- できなかったことが「できるようになった」瞬間を一緒に言葉にする
- 定期的に動画を撮影し、数週間前のプレーと見比べてみる
- 成功回数やチャレンジ回数を記録して、視覚的に積み上げを確認する
成長を感じられる仕組みがあると、子どもは自然と前向きになり、自主的に練習へ向かうようになります。そのため、成長を見える化する仕組みを作りましょう。
小学生がサッカーで上手くなるための5つの方法


子どもがサッカーで伸び悩む背景には、環境や取り組み方に原因があります。一方で、上達している子どもたちは、普段の生活や練習の中で、自分なりの工夫を積み重ねているのが特徴です。
ここでは、小学生がサッカーで上手くなるための5つの方法を解説します。
- ボールタッチの基礎を「量」で積む
- 判断力を鍛えるミニゲーム形式を取り入れる
- 毎日続けられる自主練メニューを作る
- サッカーノートを作成する
- 「声かけ」と「習慣」で楽しい環境を作る



これらの取り組みは、どれも特別な道具や指導がなくても始められるものばかりです。お子さんのタイプに合わせて、できるところから少しずつ取り入れてみてください。
1.ボールタッチの基礎を「量」で積む
小学生年代の技術習得において、何より重要なのが「ボールに触れる量」です。
特別な練習をしなくても、日常的にボールを扱う時間が増えるだけで、足元の感覚は確実に変わっていきます。
例えば、壁当てやリフティングなどの基本的な動きでも、繰り返すうちに身体が自然と覚えていきます。ボールが足に吸い付くような感覚は、こうした積み重ねの中で養われるものです。
また、ボールタッチの量が増えることで、プレー中の判断や反応もスムーズになります。週に数回のチーム練習だけでは触れる機会が限られるため、自宅や空き時間での自主練が効果的といえるでしょう。



毎日10分でも続けることで、自信や安定感につながっていきます。
2.判断力を鍛えるミニゲーム形式を取り入れる
サッカーでは、技術と同じくらい「判断の速さ」が求められます。
どこへ動くか、誰にパスを出すかなど、瞬時の選択が試合の結果を左右するためです。その力を育てる方法として効果的なのが、ミニゲーム形式の練習です。
例えば、2対1や3対2のような少人数の対人プレーは「ボールを持つ」「味方を使う」「相手をかわす」といった複数の選択肢を同時に考える機会を与えてくれます。
試合に近い状況で判断を繰り返すことで、頭と身体を連動させながらプレーする感覚が養われます。広いグラウンドがなくても、限られたスペースで十分に実施可能です。



上達している子どもほど、こうした「状況の中で考える練習」に慣れています。繰り返すことで判断が速くなり、プレーの質も安定していくでしょう。
3.毎日続けられる自主練メニューを作る
自主練の習慣をつけるうえで大切なのは「毎日できる」ことを前提にメニューを設計することです。
練習のハードルが高すぎると、続けること自体が負担になり、結果的にやらなくなってしまいます。
例えば、リフティング30回、壁パス50回といったように、短時間で終わる内容から始めると継続しやすくなります。メニューは1〜2種に絞り、その日の気分や体調に合わせて柔軟に変えても問題ありません。
重要なのは「量」よりも「頻度」です。毎日ボールに触れることで感覚が途切れず、自然とプレーの安定感が増していきます。
また、メニューを記録したり、できた回数を見える化したりするとモチベーションの維持にもつながります。



小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな自信となってプレーに表れるでしょう。
4.サッカーノートを作成する
サッカーの上達には、ただ練習を重ねるだけでなく「振り返る習慣」を持ちましょう。
プレー中に何を考え、どう感じたかを整理することで学びが定着しやすくなります。そこでおすすめなのが、サッカーノートの活用です。以下のような項目を簡単に書き残していきます。
- 今日の練習で上手くいったこと
- 上手くいかなかった理由
- そのとき自分がどう動いたか
- 次回の練習で意識すること
言葉にする過程で、自分のプレーを客観的に見る力が育ちます。書く内容は1〜2行でも十分で、大切なのは日々の気づきを積み上げていくことです。
また、ノートを通じてお子さんと会話をするきっかけにもなります。何を考え、どんな悩みがあるのかを知ることで、サポートの質も自然と高まっていくでしょう。



思考と行動がつながることで、より深い成長につながります。
5.「声かけ」と「習慣」で楽しい環境を作る
子どもがサッカーを続けていくうえで、技術以上に大切なのが「楽しさ」を感じられる環境です。
どれだけ良い練習メニューがあっても、気持ちが乗らなければ身につきません。そこで、効果的なのが日々の声かけと習慣づくりです。
例えば「今日はどこが上手くできたと思う?」という問いかけは、自己肯定感を高めるだけでなく、考える力も育てます。
また、練習後に一緒に振り返る時間を少しだけ持つだけでも、継続の意欲が変わってきます。結果を求めすぎず、チャレンジした過程に目を向けて声をかけることが大切といえるでしょう。



安心して取り組める環境があることで、子どもは自然と前向きになり、自分から動けるようになります。
小学生におすすめなサッカーの自主練メニュー10選


小学生のうちに自主練に取り組むかどうかで、今後の成長を大きく左右します。ただし、やみくもに練習しても効果は上がりにくく、正しい練習が必要です。とくに小学生年代では、楽しさと成長の実感を両立できるメニューが理想です。
ここでは、小学生におすすめなサッカーの自主練メニュー10選紹介します。
- インサイドタッチ
- インロール
- ダブルタッチ
- インアウト(右足)
- インアウト(左足)
- V字インタッチ
- 足裏タッチ
- 横移動足裏タッチ
- V字インアウト(右足)
- V字インアウト(左足)
ちなみに、本記事で解説する自主練メニューは、以下のYouTube動画でも解説しています。実際に動画を見ながら、一緒にお子さんと練習してみてください。
1.インサイドタッチ
インサイドタッチは、サッカーのすべての基礎に直結する重要なボールコントロールのひとつです。
左右の足の内側(インサイド)を使って交互にボールを運ぶことで、足元の感覚を養い、試合中の安定したプレーにつながっていきます。
- 左右交互にリズムよくボールをタッチする
- 足元からボールを離さないように意識する
- 無理に速くやろうとせず、まずは正確なタッチを反復する
小学生のうちは、動きが大きくなったりボールが足から離れてしまいがちですが、この練習を繰り返すことで、細かくボールを扱う感覚が自然と身についてきます。
移動しながらタッチする練習に発展させることで、より実戦的な動きにも対応できるようになります。
2.インロール
インロールは、足の裏でボールを内側に転がすシンプルな動作です。
ボールをコントロールしながら動きに緩急をつける力を身につけられ、実戦では相手との駆け引きやボールの持ち運びに役立つ重要なスキルでもあります。
- 足裏でボールを内側へゆっくり転がす
- 軸足との位置関係を意識し、バランスよく行う
- 左右両足で同じように動かせるように練習する
とくに小学生年代では、足裏の感覚を育てる意味でも非常におすすめです。
利き足だけでなく逆足でも取り組むことで、どちらの足でもボールを扱えるようになり、プレッシャーのかかる場面でも落ち着いて対応できるようになります。
3.ダブルタッチ
ダブルタッチは、ボールを横にずらして相手をかわす基本的なフェイントのひとつです。
片足のインサイドでボールを外側へ動かし、すぐに逆足のインサイドで反対方向へ持ち替える動作で、シンプルながら実戦でも使いやすいスキルです。
- 左右の足で連続してインサイドタッチを行う
- ボールを動かす方向をはっきりと出す
- 切り返しのときに体ごと移動する意識を持つ
タイミングよく使うことで、相手の重心を外して突破につなげられます。とくに1対1の場面や、狭いエリアで前を向きたいときにおすすめです。
また、最初はその場でゆっくり動かしながらフォームを確認し、慣れてきたらスピードや切り返しの角度を変えて実践的な動きに近づけていくと効果的です。
4.インアウト(右足)
インアウトは、同じ足でボールを内側(イン)から外側(アウト)と連続してタッチする動きです。
細かいタッチを繰り返すことで、足元の器用さと方向転換の感覚を養えます。
- 右足でインサイド→アウトサイドの連続タッチを行う
- ボールを大きく動かさず、足元で細かく扱う意識を持つ
右足だけで操作する練習を通じて、利き足のコントロール精度を高めるだけでなく、相手の逆を突く感覚も自然と身についてきます。
シンプルな動きではありますが、試合中の1対1や突破の起点として使える場面が多く、実戦性の高いメニューです。
5.インアウト(左足)
続いて、インアウトの左足バージョンです。
苦手意識を持ちやすい左足の操作ですが、毎日のように触れることで確実に慣れていきます。
- 左足でインサイド→アウトサイドの連続タッチを行う
- ボールを大きく動かさず、足元で細かく扱う意識を持つ
試合では右足だけでは対応しきれない場面も多く、両足を自然に使えることがプレーの安定感につながります。
最初は上手くいかなくても、動かし方やタイミングを体で覚えていくことが大切です。
6.V字インタッチ
V字インタッチは、ボールを足裏で引いてからインサイドで押し出す動きを繰り返す練習です。
ボールを自分のコントロール下に置いたまま、素早く方向を変える動作が身につくため、ドリブル中のターンや方向転換の精度が高まります。
- 足裏でボールを引いてからインサイドで斜め前に出す動きを繰り返す
- 左右交互に行い、バランスよく体を使うことを意識する
- V字の角度を意識しながら、リズムよく続ける
この動きは、狭いスペースでも繰り返し練習できるうえ、ボールと体を同時に動かす感覚を養えるのが特徴です。
最初はゆっくり丁寧に行い、慣れてきたらリズムやテンポを意識して取り組むとより効果的です。
7.足裏タッチ
足裏タッチは、ボールを足の裏で前後にコロコロと転がすシンプルな動作です。
細かいタッチの感覚やボールとの距離感を養えるため、小学生におすすめな練習メニューとなっています。
- ボールを足裏でタッチする
- 体の真下でタッチする位置を意識する
- 左右交互に行い、両足で同じように動かせるようにする
とくに小学生年代では、インサイドやアウトサイドだけでなく、足裏でボールを扱う感覚を育てることが今後のプレーの幅にもつながります。
足裏の感覚が身につくと、ターンやキープ、ボールを落ち着かせたい場面で自然と選択肢が広がるでしょう。
8.横移動足裏タッチ
横移動足裏タッチは、ボールを足裏で左右に転がしながら、身体も横方向へ動かしていく練習です。
足裏でボールをコントロールする感覚に加え、左右への動き出しやバランス感覚も同時に養えます。
- ボールを足裏で左右に転がしながら、体ごと横に移動する
- 目線を下げすぎず、周囲も見ながら動く意識を持つ
- 体が浮かないよう、やや腰を落として安定した姿勢で行う
守備をかわしたり、パスコースを作ったりるときなど、試合中に横へ動く場面は多くあります。その際にスムーズにボールを運べるようになるには、足裏での操作に慣れておくことが大切です。
動きながらボールを扱うため、最初はゆっくり丁寧に行うのがおすすめです。慣れてきたらテンポやスピードを上げて、試合に近い動きへと発展させていきましょう。
9.V字インアウト(右足)
V字インアウト(左足)は、右足裏でボールを斜め後ろに引き、インサイドで押し出す動きを繰り返す練習です。
ボールの動きがVの字を描くようになるため、名前の通り「V字」の感覚を身につけながら取り組めます。
- 足裏で斜め後ろに引き、右足インサイドで押し出す動きを繰り返す
- ボールが足から離れすぎないようにコントロールする
- 動作をなめらかにつなげてリズムを保つ
右足だけで行うことで、利き足の操作精度を高められ、試合中の細かいボールコントロールや方向転換にもつながります。
「ボールを引く」「運ぶ」「戻す」という連続動作の中で、自然と軸足の使い方や姿勢の安定も養われていきます。
10.V字インアウト(左足)
V字インアウト(左足)は、左足裏で斜め後ろに引き、インサイドで押し出す動きを繰り返す練習です。
非利き足での細かいボールタッチに慣れることで、試合中のプレーの幅や対応力が広がっていきます。
- 足裏で斜め後ろに引き、左足のインサイドで押し出す動作を繰り返す
- タッチの強さと距離を一定に保つ意識を持つ
- 動作の流れを止めず、リズムよく続けることを意識する
最初はぎこちなく感じるかもしれませんが、繰り返すうちに少しずつ感覚が身についてきます。
片足だけで引いて押す動作を行うため、ボールコントロールと同時に軸足のバランス力も養われる点が特徴です。
小学生がサッカーでドリブルを上手くするための3つのポイント


ドリブルが上手くなるには、ただボールを触る回数を増やすだけでは不十分です。ボールの扱い方だけでなく、身体の使い方や相手との駆け引きなど、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、小学生がサッカーでドリブルを上手くするための3つのポイントを解説します。
- ボールを見ずに運ぶ感覚を養う
- 軸足の動きと姿勢を安定させる
- 「相手との間合い」を意識した練習をする
サッカーでドリブルが上手くなりたいお子さんは、以下のYouTube動画も参考にしてください。
1.ボールを見ずに運ぶ感覚を養う
ドリブル中に顔が下がってしまうと、相手や味方の位置が見えず、プレーの選択肢が狭まります。
サッカーにおいて「顔を上げたままボールを扱える力」は、判断スピードや視野の広さにもつながります。とはいえ、最初からボールを見ずに運ぶのは難しいため、足元の感覚を育てる段階的な練習が必要です。
例えば、目線を上げた状態でインサイドタッチを繰り返す、壁に貼ったマークを見ながらリフティングするなど、感覚を養う工夫を加えるのがおすすめです。
「見る」のではなく「触って感じる」ことで自然と顔が上がり、視野を確保した状態でプレーできるようになります。



視線を上げる習慣が身につくと、パス・シュート・突破といった判断が格段にスムーズになります。
2.軸足の動きと姿勢を安定させる
ドリブルが安定しない理由のひとつに、軸足の動きや姿勢の崩れがあります。
ボールを扱う足ばかりに意識が向くと、体のバランスが取れず、余計な動きが増えてしまうことも少なくありません。
軸足が安定していると、タッチの位置がぶれにくくなり、体全体をスムーズに動かせるようになります。とくに重心をやや低く保った状態をキープできると、方向転換やストップ動作にも対応しやすくなります。
練習の中では片足立ちでのステップや、ゆっくりしたスピードでの切り返し動作など、体の軸を意識したメニューを取り入れるのが効果的です。



姿勢が整うことで、ドリブルだけでなく他のプレーにも安定感が生まれてきます。
3.「相手との間合い」を意識した練習をする
ドリブルは、単にボールを運ぶ技術ではなく「相手との距離感=間合い」をコントロールする力が問われるプレーです。
相手が届かない位置を保ちながら、自分が有利に仕掛けられる距離を見極められる選手ほど試合でドリブルが通用します。
この感覚を身につけるには、コーンを相手に見立てた1対1形式の練習が効果的です。相手との距離をキープしたまま角度を変えたり、逆を取る動きにつなげたりすることで、実戦に近い判断と動きが養われます。
また、あえて近づいてから一気に離れるなど、間合いのズラし方を意識することも重要です。距離とタイミングをコントロールできるようになると、無理にスピードやテクニックに頼らなくても抜けるドリブルが生まれてきます。



間合いは小学生のうちから意識して取り組んでおくと、将来大きな武器となりやすいです。
小学生がサッカーでシュートを上手くするための3つのポイント


シュート力を高めるには、筋力だけに頼るのではなく、正しいフォームや身体の使い方を理解することが重要です。とくに小学生のうちは、ボールを強く蹴ろうとして力任せになり、かえってフォームが崩れてしまうことも少なくありません。
ここでは、小学生がサッカーでシュートを上手くするための3つのポイントを解説します。
- 助走のスピードとリズムを意識する
- 軸足の踏み込みでインパクトを強くする
- 足を速く振り抜くフォームを習得する
シュートが上手くなりたいお子さんは、以下のYouTube動画も参考にしてみてください。
以下の記事では、サッカーのシュートを上達させるコツも解説しています。


1.助走のスピードとリズムを意識する
強いシュートを打つうえで、ボールを蹴る直前の助走が速くスムーズであるほど、インパクト時に力が伝わりやすくなります。
反対に、助走が遅かったり途中でブレーキをかけたりしてしまうと、勢いが失われて弱いシュートになってしまいます。
大切なのは、ただ速く走るのではなく「リズムよく加速すること」です。とくに最後の2〜3歩でスピードが乗るような助走を意識すると、自然と足が振りやすくなり、インパクトも強くなります。
助走の歩幅やテンポは人によって合う形が異なるため、繰り返し試しながら自分に合ったリズムを見つけていくことが大切です。



フォームや筋力に頼る前に、まずは助走の入り方を見直すだけで、シュートの威力が大きく変わることもあります。
2.軸足の踏み込みでインパクトを強くする
強いシュートを打つためには、蹴る足だけでなく「軸足」の使い方が重要なポイントです。
軸足がしっかり踏み込めていると、地面を踏んだ反動がそのままキックの力につながり、インパクトが強くなります。
とくに小学生年代では、ボールに意識が集中しすぎて軸足が浅くなったり、バランスが崩れた状態で蹴ってしまったりすることがよくあります。しかし、これでは力が伝わりません。
ポイントは、ボールのやや横・少し手前に軸足を踏み込むことです。深く、安定した踏み込みができると体全体の力が乗りやすくなり、自然と強いキックにつながります。



シュートが弱いと感じるときは、足の振りだけでなく「軸足の位置」や「踏み込みの深さ」にも目を向けることで、改善の糸口が見えてくるはずです。
3.足を速く振り抜くフォームを習得する
シュートの威力を上げるためには、インパクトの瞬間だけでなく「足の振り抜きスピード」も大切です。
ボールを強く押し出すためには、助走の勢いに加えて、足を速く振り切る動作が必要になります。
とくに小学生は、フォームが不安定だったり、インパクトの直後で力を抜いてしまったりすることで、ボールに十分な力が伝わらないケースが多く見られます。力任せに蹴るのではなく、正しいフォームでスムーズに足を振り抜くことがポイントです。
- 助走でスピードを乗せる
- 軸足をしっかり踏み込む
- 蹴った後まで振り切る意識を持つ
腕の振りや体のひねりを活かしながら、自然とスピードに乗った足の振りができるようになると、シュートの質が大きく変わってきます。



フォームを整えるだけで、力に頼らず鋭いボールが蹴れるようになるため、ぜひ時間をかけて取り組みたいポイントです。
子どものサッカーを上手くするための親の関わり方


子どもがサッカーを楽しみながら上達していくためには、日々の練習だけでなく、家庭での関わり方も影響を与えます。技術的なことはコーチに任せるとしても、家庭でメンタルや自信を成長させていきましょう。
ここでは、子どものサッカーを上手くするための親の関わり方を以下の点に分けて解説します。
- 声のかけ方
- 自信の育て方
- 練習環境の整え方



日常のちょっとした声かけが、子どものやる気や自信につながります。まずは、成長を促す声かけのポイントから見ていきましょう。
1.声のかけ方
実は子どもがサッカーに前向きに取り組めるかどうかは、親の声かけひとつで大きく変わります。
東京未来大学の「小学生のスポーツ活動における保護者の関わり」によれば、保護者の声かけによっては、子どものやる気やチーム内の関係に悪影響を与えることもあると報告されています。
良かれと思ってかけた言葉が、無意識のうちにプレッシャーや自信喪失につながることもあるため、伝え方には細やかな配慮が必要です。
例えば「なんでできないの?」という否定的な言葉は避け、「チャレンジしたのがよかったね」「今日はどこが楽しかった?」といった前向きな声かけを意識しましょう。
また、結果よりも努力や工夫に目を向けて言葉をかけることが、継続する力や自信を育てる土台になります。



上手くいかないときこそ寄り添い、成長のきっかけになるような言葉を選ぶことが大切です。
2.自信の育て方
サッカーにおいて「自信」は、技術や体力と同じくらい重要なポイントです。
自信がある子どもは、ミスを恐れずにプレーでき、積極的にチャレンジする姿勢を持ち続けられます。一方で、失敗を繰り返したり、周囲からの比較が多くなったりすると、自信を失いやすくなるのも小学生年代の特徴です。
親の関わり方としては、結果ではなく「努力」や「取り組む姿勢」に注目して声をかけましょう。
例えば「今日のドリブル、よく頑張ってたね」といった具体的な場面を認めるだけで、子どもの中に達成感が残りやすくなります。自信は成功体験だけでなく「見守られている安心感」の中でも育っていきます。



プレーの前後や練習後の会話の中で、前向きな言葉をかけてみてください。
3.練習環境の整え方
サッカーの上達には、日々の練習に集中できる環境が必要です。
とくに小学生年代では、練習環境の差がそのまま成長スピードに表れてきます。
とはいえ、特別な設備や広いスペースが必要というわけではありません。自宅前のちょっとしたスペースや公園でも、壁当てや足元のボールタッチなど、できることはたくさんあります。
大切なのは、子どもが「またやりたい」と思えるような、続けやすい環境を用意してあげることです。
また、練習時間を決めて習慣化したり、終わったあとに少し会話したりするだけでも、安心感とモチベーションにつながります。親がそっと見守るだけでも、子どもにとっては大きな支えとなるでしょう。



プレッシャーを与えるのではなく「やってみたい」と思える空気づくりが大切です。
小学生でサッカーが上手くなりたいなら「TORIDENTEストライカースクール」


子どものサッカーを上手くするなら「TORIDENTEストライカースクール」がおすすめです。
TORIDENTEストライカースクールは、ストライカー育成に特化したサッカースクールです。ただ得点を取るだけでなく「自分で考えてプレーする力」を育てることを大切にしており、基礎から応用まで課題に応じたトレーニングが受けられます。
- ストライカーに特化したサッカースクール
- 中高生でも使えるスキルが身につく
- プレーや指導実績が豊富なコーチが在籍している
- トレーニング後に毎回フィードバックを受けられる
- スペインへのサッカー留学エージェントと提携している
子どもたち一人ひとりの思考と成功体験を引き出す声かけが特徴で、ミスを責めることなく、子どもが前向きに挑戦できる雰囲気づくりを大切にしています。
なお、TORIDENTEストライカースクールの様子は、以下の動画でご覧いただけます。
関東と沖縄を中心に展開しており、無料体験会も実施していますので、お子さんのサッカーを本気で上手くさせたい方は以下から詳細をお確かめください。
サッカーが上手くなるには楽しく続けられる環境づくりを大切にしよう
サッカーが上手くなるには、毎日少しでもボールに触れ、自分の課題に向き合いながら継続することが大切です。
チーム練習だけでなく、自主練で基礎をコツコツ積み重ねることで、試合での安定したプレーにつながっていきます。
こうした練習を続けるうえで大切なのが「やってみたい」と思える環境です。親の前向きな声かけや、小さな成長を一緒に喜ぶ姿勢が子どもの意欲を支える力になります。
子どもが自信を持って前向きに取り組めるよう、家庭でも温かいサポートを心がけていきましょう。


